大阪・関西万博2025の日本館は、開催前から大きな期待を背負っていた。
日本らしさ、技術力、文化的メッセージ──
あらゆる要素を代表する存在だったからだ。
会期中は完成度の高い展示として評価される一方で、
万博が終わった今、改めて思い返すと
「強く記憶に残っているか?」と自問したくなる人も多いだろう。
本記事では、日本館を持ち上げも否定もせず、
万博後の視点から冷静に振り返り、
なぜ評価が分かれたのか、そして次の博覧会に何を残したのかを整理していく。

日本館は“完成度が高い展示”だったのは確か
日本館は、位置的にも導線上でも万博の中心的存在だった。
建築自体の存在感もあり、屋外から見える外観は非常に整っていた。
内部展示では、
- 大型スクリーンによる映像演出
- 日本の産業・文化の歴史的文脈
- 未来技術のデモンストレーション
といった情報が豊富に提供されていた。
特に映像は美しく、内容も充実していたため、
その“完成度の高さ”は来場者の評価を集めた。

なぜ日本館は“正解を提示する展示”に見えたのか
日本館の展示は非常に丁寧で、テーマも明確だった。
来場者は「日本とはこういう国だ」というストーリーを一貫して受け取る。
これは一方で、
**「押しつけられた感じ」**にもつながりやすかった。
例として、
- 展示解説が文章主導
- 映像が説明中心
- 体験が情報消費に近い
という特徴は、日本館に限らず
「正解が用意された展示」に共通するパターンでもある。
この種の展示は、その場では納得感があるものの、
後から記憶として残る余白が少ない。
結果として、
「すごかった」けど、後で思い返しにくい
という評価につながった可能性がある。

派手さではなく、記憶に残る余白はあったか
日本館にも“静かな記憶”を育む瞬間はある。
例えば、
- 伝統工芸の職人技を間近で見られるゾーン
- 観客が自ら参加する仕掛けではないが
周囲の空気が落ち着いている空間
こうした部分は、
脳の処理スピードが落ちてゆっくり味わえるため、
あとから思い出されやすい。
これは、派手な演出とは別の
**感情の“余韻”**を残すタイプの展示だ。

海外パビリオンと比べて見えた日本館の特徴
海外パビリオンの中には、
- アメリカ館
- 中国館
- 北欧館・バルト館
など、さまざまなアプローチがあった。
特に北欧館やバルト館の展示は
「説明しすぎず余白を残す」タイプが多く、
あとから思い出されるケースが多かった。
(この傾向はこちらの記事で詳述した通り)
一方で、アメリカ館や中国館は
大規模マルチメディア演出でその場の没入感は高いものの、
体験がその場で完結しやすい構造でもあった。
この対比で見ると、日本館は
「整理された情報の洪水」の中に、
静かな余白と強いメッセージが混在していた、
という評価ができる。
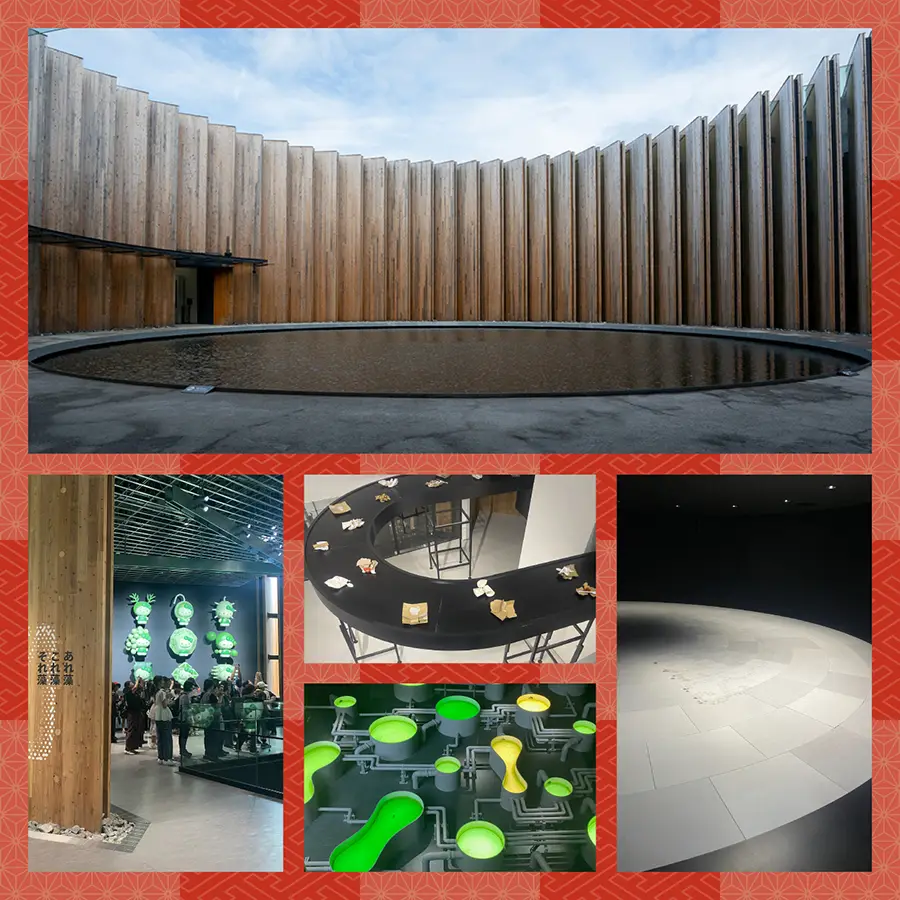
横浜園芸博で日本館的アプローチはどう活きるか
横浜園芸博は、
植物・自然・季節を主役に据えたテーマ性のイベントだ。
そこでは「情報を理解すること」が主目的ではなく、
- 体感
- 感じる
- 空間と時間の共有
という種類の展示が強く評価される。
この点で、日本館の展示の中にあった
**「余韻を大切にする空間創り」**や
**「押しつけない情報提示」**の要素は、
これからの博覧会設計にとても重要になる。
あとから思い返したくなる展示とは何か
ここまで見てきたように、
パビリオンや展示の印象が残るかどうかは、
- 一瞬の驚きより
- 余韻、余白、滞在しやすさ
という条件と密接に関係する。
これは、建築や動線設計とも深くつながる。
(関連記事)
万博会場は歩きやすかったのか?夢洲で分かった動線の差
まとめ
日本館は「学び」も「体験」も高い展示だった
しかし…
完成度が高すぎる展示は、
その場で評価されやすい反面、
後から思い返されにくいという面も持っている。
これは日本館の弱点ではなく、
「展示のあり方」を考える上で、
非常に重要な気づきだ。
次の横浜園芸博では、
この認識を踏まえた
- 余白をつくる展示
- 考えさせる体験
- 立ち止まって味わえる空間
が、より重要になっていくだろう。